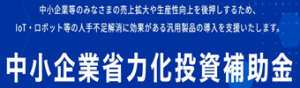自営業・個人事業主の引退後の資金は現役時代に自助努力しておくしかない!
全国でおよそ133万人の経営者が加入されています。
小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建をはかるための資金をあらかじめ準備しておく制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
制度の位置づけ

一般的に自営業者の方にとって、将来の生活資金として考えられるのは国民年金の基礎部分がありますが、20歳から60歳まで保険料を満額払い込んでも、65歳から受取る基礎年金額は、月額約6万4千円。これだけでは生活費としては足りません。
課題としては、国民年金に加えて何か準備しておく必要があります。右図のように年金を補完する商品群の1つとして「小規模企業共済」は位置づけることができます。
主な特徴
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。(最高84万円の所得控除が可能)
- 共済金の受取りは退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い。
- 掛金は月額1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定可能、増額や減額もできます。
- 個人事業の廃止の場合、共済金の額は、掛金を概ね年1.5パーセント相当で複利運用した額となります。
- 共済金の受取りは「一括」、「分割(10年、15年)」、「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。(ただし、分割受取には条件があります。)
- 急な事業資金が必要になった場合などに担保、保証人不要で貸付制度が利用できます。
- 共済金受給権は差し押さえ禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等の場合を除く)
- 国が出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営をしています。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※共同経営者とは事業主と共に経営に携わっている方で
「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
「事業の執行に対する報酬を受けている」
少なくともこの2つを満たす方となります。
個人事業の共同経営者が小規模企業共済に契約を申込む際には、共同経営者としての要件を証明するための書類が必要です。
見本を参照のうえ証明書を作成ください。
共同経営契約書見本
ダウンロード(ワードファイル)
パンフレット
小規模企業共済制度パンフレット
ダウンロード(PDFファイル)
小規模企業共済制度のしおり
ダウンロード(PDFファイル)
動画紹介
もっと知りたい 小規模企業共済(YouTube動画)
将来の受取り共済金額と節税額の試算が簡単にできます
中小機構のホームページで加入シミュレーションを行うことが出来ます。
加入シミュレーション
「掛金払込証明書」の再発行について
確定申告時に必要な『掛金払込証明書』を紛失して再発行を依頼する際の手続き方法です。
中小企業基盤整備機構ホームページ上の『掛金控除証明書』再発行専用フォームまたはお電話(自動音声ガイダンス)から、『掛金払込証明書』の再発行を申請いただけます。
詳細はこちら→中小企業基盤整備機構ホームページへ移動する
加入・給付金請求、その他諸手続きは
久留米商工会議所へお問い合わせください
久留米商工会議所 地域振興課
電話:0942-33-0212 (受付時間 平日:午前9時から午後5時30分)
制度運営先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
九州支部 電話:092-263-1500
共済相談室 電話:050-5541-7171 (受付時間 平日:午前9時から午後6時)